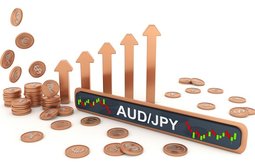用語集

【A~Z】
CME (Chicago Mercantile Exchange)
米国シカゴにある世界最大規模の先物取引所のこと。
EFSF債 (European Financial Stability Facility)
EU(欧州連合)が通貨ユーロ防衛のために創設した「EFSF=欧州金融安定基金」が発行する債券。 EFSFは資金支援が必要になったアイルランドなどユーロ加盟国に融資するため、最大で4400億ユーロの政府保証付き金融安定化債を発行できる。
MACDプリディクター (macd predictor)
ディナポリのツールのひとつ。 MACDのラインをローソク足チャート上に描画したもの。
mio
million(ミリオン)の略。 1,000,000(100万)のこと。 インターバンク市場での最小取引単位となっている。 1本=100万通貨単位
NFP
Non Farm Payrollの略、非農業部門雇用者数のこと。 米国の雇用統計とは、この非農業部門雇用者数と失業率、平均時給など雇用関連指標をセットにした呼称である。また雇用統計をNFPと言う場合もある。
QE (Quantitative Easing)
中央銀行が金利の引き下げ余地がなくなって、さらに金融を緩和する場合に、市場に直接資金を供給し、中央銀行の当座預金残高量を拡大させる金融政策。 金利調節ではないため、量的金融緩和、量的緩和と言われる。
金利調節が中央銀行による通常の金融政策であることから「伝統的金融政策」と言われるのに対して、量的緩和は「非伝統的金融政策」とも言われる。
TDコンボ (TD-Combo)
トム・デマーク開発のテクニカル指標のひとつ。TDシーケンシャルのデリバティブ版。カウントダウンの仕方がTDシーケンシャルと異なる。
TDシーケンシャル (TD Sequential )
チャート分析における世界の第一人者として広く知られているトム・デマークが開発したテクニカル指標。逆張りテクニック。 マーケットのトレンドの持続の中にはset upとcountdownがある。
set upは9でいったん終了。9が示現すると、いったんそのトレンドが調整に入る可能性がある。次にcountdownというトレンドが始まる。countdownの終了は13。
TDレイ (TD-REI)
トム・デマーク開発のテクニカル指標のひとつ。オシレーター系のインディケータ。
WMRフィクシング
ロンドン午後4時の値決め、通称WMR、世界の機関投資家の仕切り値のベンチマーク。多額の注文が入るため不正を指摘する声もあった。過去には英FSAが大規模な調査に乗り出し、摘発され業界を去る者がいた。特に月末最後の2日間は特に注意。
関連記事:
ロンドンフィクシングとは何?トレードにどう活かすのか?
https://real-int.jp/articles/44/
【ア行】
アールシーアイ (RCI )
Rank Correlation Indexの略。順位相関指数のこと。相場の過熱感を測り、いま現在の価格が割安か割高かを判断するときに使用されるテクニカル指標。
アールビーエイ (RBA)
Reserve Bank of Australiaの略。オーストラリア準備銀行(中央銀行)のこと。
アールビーエヌズィー (RBNZ)
Reserve Bank of New Zealandの略。ニュージーランド準備銀行(中央銀行)のこと。
アイエムエム (IMM)
International Monetary Marketの略。CMEにある国際通貨市場のこと。
アウト・オブ・ザ・マネー (out of the money)
略してOTMともいう。オプション取引で権利行使価格(ストライク)に到達していない状態のこと。
アウトパフォーム
金融商品などで、同一グループ内の他の銘柄に比べて期間収益が上回っていること。反対が「アンダーパフォーム」。
アクティブ運用
市場平均を上回るように、運用担当者の見解、場合によっては相場観で銘柄選択を下し運用成績の向上を図る運用方針。反対は「パッシブ運用」
アグリーメント (agreement)
フィボナッチ・リトレースメントとフィボナッチ・エクスパンションが重なるポイント。強い抵抗。
アスク (ask)
通貨を買う時の値段 。
アセットクラス
同じような特徴やリスクを包含する一塊の投資対象。クラスということから種類、仲間を意味する。
アセットマネジャー
個人・法人問わず、投資家より委託された資金を効率的に管理運用する人。
アノマリー
通常、ある法則や規則からは説明できない規格外の現象を差す。相場の世界では、「理論的な根拠が無いものの、よく当たることから、この先も繰り返されるのではないかと予想される経験則」を意味する。
アベレージング
平均化。このスレッド内の意味は、買いコストまたは売りコストの平均化を意味する。
アンダーウエイト
資産運用において、市場平均より当該カテゴリー(株、債券、商品、不動産、現金比率等)、銘柄の比率を市場平均より抑えること。反対はオーバーウエイト。
この組み換えが市場の変動に結び付くことから注目となる。特にグローバルでのファンドマネージャー等は、概して同一の投資判断を下すこと多い。中長期での相場の流れを形成することから、組み換えの変化は常に注意しておく必要がある。
アンダーパフォーム
金融商品などで、同一グループ内の他の銘柄に比べて期間収益が下回っていること。反対が「アウトパフォーム」。
アンワインド
ポジションを決済すること。ポジションの「巻き戻し」の意味にも使われる。
イーシービー (ECB)
European Central Bankの略。欧州中央銀行のこと。ユーロ圏の金融政策を行っている。
イールドカーブ
債券市場における金利曲線。住宅ローン金利に象徴されるように期間が長い程金利は高くなり、原則一次曲線を描く。
行って来い
いってこい。相場の格言。相場がある水準まで上昇した後に、元の水準まで下落すること。下落後に上昇して元に戻っても同じ。
インカムゲイン
金融資産を一定期間保有することで得られる現金収入。銀行預金であれば受取利息、債券ではクーポンからの利金、為替であればスワップポイント(為替の場合はネガティブの場合もあり)。
インフレファイター
中央銀行の金融政策において、インフレを抑制的にコントロールし、物価の安定を最重要視する金融当局者、中央銀行。
永久債
償還期限の無い債券を意味する。この数年意識されているのは償還期限のある国債を永久債化した場合。これは中央銀行を引受先とさせる財政ファイナンス。究極のヘリコプターマネーで、通貨の信認暴落、通貨安に直結する。
エイチアイエイ (HIA)
Homeland Investment Actの略。 HIAは2000年代前半に行われた米国の本国投資法で、米国の多国籍企業が海外で稼いだ滞留資金を米国内に送金する時に課税を免除するという政策。
エクスパイア (expiry)
金融派生商品(デリバティブズ)の期限、期日、消滅
エスエヌビー (SNB)
Swiss National Bankの略。スイス国立銀行(中央銀行)
エックスオーピー (XOP)
expanded objective pointの略。フィボナッチ・エクスパンションによる目標値のひとつで、161.8%レベル。
エマージング市場
日本語では新興国市場。かつての教科書的表現では「発展途上国」、経済発展も目覚ましく、先進国からの投資も受けやすい。信用リスクという観点ではやや低く、その分高金利であり資金の受け皿となりうる。ただ世界の資金の逆流にはぜい弱。
エフアールビー (FRB)
Federal Reserve Boardの略。アメリカの連邦準備制度理事会のこと。アメリカの公定歩合や支払い準備率の決定など金融政策や金融機関の監視を行っている。
エムエー (MA)
Moving Averageの略。移動平均線のこと。
200 days MA=200日の移動平均線(過去200日間の終値の平均値)
エルティーアールオー (LTRO)
Long Term Refinancing Operationの略。流動性供給オペレーションのこと。 欧州中央銀行(ECB)が市場の流動性を高める銀行信用の収縮を打開するために導入された。
2008年秋のリーマン・ショックまでは、LTROの期間は2週間、1ヶ月、最長でも3ヶ月までだったが、その後、ECBは6ヶ月、1年とLTROの期間を拡大していった。2011年12月には、3年物のLTROが誕生した。
円転
既に外貨運用している資金を円に戻すため、「外貨売り、円買い」を実施すること。外貨資金を原資に円資金を調達すること。外貨資金を円資金に換えて運用すること。
オージー (ozz)
オーストラリアのこと。 ozと略す場合もある。
オーバーウエイト
資産運用において、市場平均より当該カテゴリー、銘柄の比率を市場平均より多めにすること。反対がアンダーウエイト。
オーバーソルド (oversold)
売られ過ぎのこと。
オーバーナイト・インデックス・スワップ(OIS)
翌日物のレートと数週間から2年程度までの固定金利を交換スワップ取引。中央銀行の政策金利の変更の織り込み度合を計る時に使われる。
オーピー (OP)
objective pointの略。フィボナッチ・エクスパンションによる目標値のひとつで、100.0%レベル。
オープン外債
国内の機関投資家の外債投資の中で、ヘッジを付けていない外債投資のこと。ヘッジが付いていないので、実弾での実質外貨買い・円売りを伴う。反対が「ヘッジ外債」
オファー (offer)
売りの注文。92円台のオファーが増えてきているというのは、92円台で売りの注文が増えてきているという意味。
オプション (option)
将来のあらかじめ決められた一定期日の中で、権利行使価格で取引する権利のこと。
オペレーション (operation)
運用、運営、動き方。
終値
初値(寄値)、高値、安値、終値という4本値のひとつ。別称「引値」、ある一定の時間軸(5分足、1時間足)で最終的に取引された価格(最終的な気配値を含める場合もあり)。終値を投資判断に広く用いる場合があり重要視される。
【カ行】
外国為替平衡操作
財務省の権限で実施されるいわゆる為替介入。通常財務省の指揮のもと、日本銀行が主要邦銀・外資系銀行に対し行う。
カウントダウン (count down)
TDシーケンシャルの専門用語。セットアップが9で終了後のトレンドの再開。13で終了とみなす。
カストディ
投資家に代わって、株式や債券などの有価証券の保管・管理を行う金融機関のこと、カストディアン。
カストディーアカウント(custody accounts)
保護預かり、保護預かり勘定のこと。
カレンシーオーバーレイ
外債・外株などの外貨建て資産の為替部分を原資産から分離し、運用能力の高い外部の専門家に為替部分のみの委託運用を行うこと。
キウイ(kiwi )
ニュージーランド・ドル(NZD)のこと。ニュージーランドの国鳥のキウイからきている。キウイフルーツのことではありません。
キャピタルゲイン
株・債券・為替等の保有資産を売却することによって得られる売買差益。反対はキャピタルロス。
キャリートレード
一般的に、金利の低い通貨で資金調達(ファンディング)してより高金利の通貨を買い建て、日々スワップ金利を狙っていく取引を指す。こうした場合、市場の変動率が小さいほどキャリートレードには有利で、より多くの投資家がキャリートレードに収益を求めることになる。
金利差
同一の金融商品内での金利の差のこと、日米金利差では同一期間での国債の「利回り格差」。
グリーク(オプションのリスク指標)
オプションの値段を決める4つの要素(デルタ・ガンマ・ベガ・セータ)のこと。この数字を見ることでそのオプションの性格を知ることができ、今後の値動きを予想できる。
グリーディ(greedy)
「欲張り」という意味 。
グレグジット (Grexit)
ギリシャのユーロ離脱問題からできたマーケット造語。Greece(ギリシャ)が、Exit(出口=出て行く)をつなげて、ギリシャのユーロ圏離脱をGrexitと言う。
クレジットリスク
金融などの取引において、債務者の財務状態が悪化することによって、債権の回収ができない状態に陥るリスクのこと。
グローバルマクロ(global macro)
世界中のあるゆる市場(株、通貨、商品など)をマクロ分析をして、ある投資対象に方向性がでるや、集中的に投資する手法をとるファンド。
ディレクショナル(方向性)を取りにいく手法であり、ヘッジファンドの代表格。有名なグローバルマクロとして、ジョージソロス氏が率いる「クオンタムファンド」がある。
限月(げんげつ)
オプションの個別銘柄には全て満期日(SQ清算日)があり、売買はその前日の15:15で終了する。例えば、1月限のオプションの満期日は1月の第2金曜日。 225オプションと225先物ミニの限月は毎月。(年間12回) 先物ラージは3か月に1度。(3,6,9,12月の年間4回)
原資産
225オプションや225先物の原資産は日経平均株価。金融派生商品(デリバティブ)が売買の対象としているもののこと。
コアショート(Core short)
コアのショート・ポジションのこと。
コアポジション(core position)
トレンドの最初から最後まで、大きな値幅をとるためのポジション。条件として、トレンドの継続が見込まれることと、エントリーの位置が深いこと。
国際金融協会
略してIIF、国際金融システムの安定を維持するために設立された国際機関。70か国を超える国地域と500程度の民間金融が参画している。
国債の償還
国は国債を発行して借金する。その国債には予め決められた期限があり、その期間が経過すると元本を一旦投資家に変換する。「償還」とはその払い戻しを意味する。
コール
オプション取引で、買う権利のこと、反対に売る権利はプット。 相場が上がりそうなら、コール・オプションを買っておけば、上がったところで権利行使して利益とすることができる。上がらなければ、権利行使せず、コールを買ったプレミアム分が損失となる。
ゴールドマン(goldman)
世界最大級の投資銀行であるゴールドマン・サックスのこと。単にGSと略される場合もある。
コモディティカレンシー(commodity currency)
資源国通貨とも呼ばれる。鉱物、ガスなどの資源や農産物などを主要な輸出品としている国の通貨のこと。代表的なものでは、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、カナダドル、南アフリカランドがある。
ゴルディロックス・エコノミー(Goldilocks Economy)
インフレでもなく、景気後退でもない適度な経済状態のこと。元々は、イギリスの童話「ゴルディロックスと3匹のくま」の主人公である女の子の名前のゴルディロックスからきている。
童話では、熊の親子の家に迷い込んだゴルディロックスが、熱すぎず冷たすぎもしないちょうど良い温かさのスープを見つけ、次にちょうど良い堅さのベッドを見つける。
コンセンサス(consensus)
市場関係者による企業業績や株価、経済指標の一致した予想数値。
コンビクション(conviction)
コンビクションリストのこと。ゴールドマン・サックスが推奨する強い買いのリスト。
【サ行】
債券入札
一定条件の下で新規の債券発行が競争入札で実施されること。当然高い価格の入札者が優先されるが、この時点で最終利回りは低い結果に。これは当該債券の先行きに強気、つまり金利の低下を見通した投資。
差金決済取引
証拠金(保証金)を業者に預託し、現物の受渡し行わずに、売りと買いの差額の授受で決済する取引形態のこと。先物・オプションの他に、FX、CFDなどが該当する。売りから入れる特徴(メリット)がある。
サポート(support)
支持線
さや抜き
裁定取引(アービトラージ)。 一般的に金利差や価格差を利用して売買しその差額を稼ぐ取引のこと。
三重底
RCIの長期・中期・短期線が-80%~-100%に近い付近で集まっている状況。 強い下降トレンド。RCIの長期・中期・短期線が-80%~-100%に近い付近で集まっている状況。強い下降トレンド。
三重天井
RCIの長期・中期・短期線が+80%~+100%に近い付近で集まっている状況。強い上昇トレンド。
シーエイチエフ(CHF)
Confoederatio Helvetica Francの略。スイスの通貨のスイスフランを表す。 Confoederatio Helveticaは、ラテン語でスイス連邦という意味。
シーエムイー(CME)
Chicago Mercantile Exchangeの略。アメリカ合衆国のシカゴにある北米最大の商品先物取引所および金融先物取引所のこと。
シーオーピー(COP)
Contracted Objective Pointの略。フィボナッチ・エクスパンションによる目標値のひとつで、61.8%レベル。
資金フロー
別名、マネーフローとも呼ばれる、広義には「お金の流れ」で、FXでは個人・企業・機関投資家などが取引で使った資金の、為替市場における流れと定義できる。
シーピーアイ(CPI)
Consumer Price Indexの略。消費者物価指数のこと。消費者が商品を購入するときの、小売価格(物価)の変動を表した指数。
シーティーエー(CTA)
Commodity Trading Avisorの略。為替市場では極めて短期の売買に終始する投機筋。広義のヘッジファンド、モデル系ファンドに限りなく近い。
ジーピーアイエフ(GPIF)
Government Pension Investment Fundの略。公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人のこと。
周辺国対独スプレッド
通常使われるのは、欧州内で信用力の高い10年のドイツ国債と欧州内当該国の10年国債の金利差。経済情勢の悪化、政治リスクの増大、債務危機等で金利差が拡大する場面がある。金利差拡大は通貨ユーロの売り要因、金利差縮小はユーロの買い要因。
受益者
金融商品等の信託において、受託者に対して、信託行為に基づいて、信託利益の給付を受ける権利(受益債権)を有する者。
順イールド
長期金利の方が短期金利よりも高くなる状況を指し、イールドカーブが「右上がりの曲線」になること。反対が「逆イールド」。
ショート(short)
売り持ちポジションのこと
ショートスクイーズ(short squeeze)
価格の上昇により、ショートポジション(売りポジション)の損切り注文(買戻し)により、更に価格が上昇することを言います。踏み上げともいう。
シングルペネトレーション(single penetration)
ディナポリチャートによる押し目買い・戻り売りの手法。別名をブレッドアンドバター(天の恵み)とも言われる。
スクエア(SQ)
ポジションを決済して、ポジションをゼロにすること。
ストキャスティックス(Stochastic oscillator)
市場の「買われすぎ・売られすぎ」を見るための、オシレーター(値幅分析)系テクニカル指標。
ストライク(strike)
オプション取引の用語。一般には、ストライクプライス(strike price)と呼ばれている。オプション取引における権利行使価格のこと。
ストラテジー (strategy)
戦略、作戦
ソブリン・ウエルス・ファンド(SWF)
政府系の資金運用機関。莫大なオイルマネーを運用する北欧ノルウェーのノルウェー政府年金基金が有名。
スラスト(thrust)
ローソク足が上昇あるいは下降しているDMAに沿って動いているディナポリ・チャートの形。
セールストレーダー (sales trader)
毎日顧客に相場動向の説明をしたり、オプション戦略のご案内するなど、顧客のケアをするトレーダー。 略して単に「セールス」とも呼ばれる。
セットアップ(set up)
TDシーケンシャルの専門用語。9が出現すると、いったんそのトレンドが調整に入る可能性があるとみる。
セットアップの9(setup9)
TD-Sequentialは、反転のタイミングを探すツールです。このため、価格が上昇して、計算式と合致する値動きとなると、売るタイミングに向けたセルセットアップ(sell setup)を開始し、1から9の数字がつけられていきます。
セットアップ9が点灯すると、一旦は上昇が止まり小休止または小反転の可能性が示されます。 価格が下がる動きの場合は、バイセットアップ(buy setup)となります。
なお、西原宏一さんが使うTD-Sequentialを勉強したい方は、「西原宏一のシンプルトレード」掲示板のデマークChartスレッドにある西原さんのDVD、またはデマークの書籍をご参照下さい。
セル セットアップ(sell set up)
売りセットアップ 。TDシーケンシャルにおいて使用される言葉。日足の場合、4日(本)前より高い終値が連続すること。
セル・オン・ラリー(sell on rally)
戻り売りのこと。「buy on dip」の反意語。
【タ行】
第一次所得収支
金融収支に計上される取引以外の、居住者・非居住者間で債権・債務の移動を伴う全ての取引の収支状況。
ダイレクション/ダレクション(direction)
方向、向き
ダウンサイド(downside)
下降、下落
打診買い
相場の方向性がまだ明確でない場合に少額買うという方法。その後、相場が思惑通りに動けば、買い増す。 逆にいけば、速やかに撤退する。
打診売り
相場の方向性がまだ明確でない場合に少額売るという方法。その後、相場が思惑通りに動けば、売り増す。 逆にいけば、速やかに撤退する。
ダビッシュ(dovish)
ハト、ハト派的のこと。慎重派、弱気、消極的。
例: 景気経済の見通しについて慎重、弱気、悲観的 政策金利の引き下げに対して積極的 政策金利の引き上げに対して消極的
対義語:ホーキッシュ/hawkish/タカ派
ダブル13(double13)
TD-Sequentialは、反転のタイミングを探すツールです。
価格が上昇すると、まずセルセットアップ(sell setup)が1から9まで続き、その後も値動きが続くとセルカウントダウン(sell countdown)が1から13まで続きます。カウントダウン(countdown)の13が点灯すると大きな反転の可能性が示唆されます。ダブル13はこのカウントダウン(countdown)の13が2回表れていることで、一度13を示しながら大きな反転下落とならず、再び上昇してセルセットアップ(sell setup)と、それに続いたセルカウントダウン(sell countdown)が表示され、2回目のセルカウントダウン(sell countdown)の13が表示された状態がダブル13(double13)です。
この場合は、13が2回点灯していて強い反転の可能性が示唆されます。価格が下落している場合は、バイセットアップ(buy setup)、バイカウントダウン(buy countdown)となります。なお、西原さんが使うTD-Sequentialを勉強したい方は、「西原宏一のシンプルトレード」掲示板のデマークChartスレッドにある西原さんのDVD、またはデマークの書籍をご参照下さい。
ダブルノータッチ・オプション(double no touch option)
ある時間内に、想定したレンジの上限・下限のどちらにもタッチしなければ、高いリターンが得られるエキゾチックオプションのこと。
ダブルレポ(Double Repo)
ディナポリが大きな方向性の転換を意識するサイン。
ダン(done)
取引成立、約定のこと。
中立金利
経済を過熱も冷やしもしない金利水準、別名自然利子率、ほぼ潜在成長率と同義。
チョッピー(choppy)
不規則に変動する。
ディーエムエイ(DMA)
Displaced Moving Averageの略。DMAは、ジョー・ディナポリ氏が使い始めたテクニカル指標で、移動平均線を先の方に移動させて表示させたものです。3×3DMA(3*3DMA)は、3SMAを3期間先(ローソク3本分先)に移動させたもの。
7×5DMA(7*5DMA)は、7SMAを5期間先(ローソク5本分先)に移動させたもの。25×5DMA(25*5DMA)は、25SMAを5期間先(ローソク3本分先)に移動させたもの。
ディップ(dip)
押し目のこと。相場が上昇トレドにあるときに価格が一次的に下がる局面。 押し目買いは「buy on dip」
ディナポリ(dinapoli)
ジョー・ディナポリ(Joe DiNapoli)氏が考案した様々なトレーディング手法を総称して使用される用語。フィボナッチ数列を様々な指標と組み合わせを編み出している。
テイラー・ルール
スタンフォード大学のジョン・ブライアン・テイラー教授が1993年に提唱した、中央銀行が誘導する政策金利の適正値をマクロ経済の指標により定める関係式。
テールリスク
リスクは文字通り危険、金融の世界では「危険度」。テールとは尾っぽ、つまり平時では想定されない、『想定外のリスクシナリオ』を示す。結果的に発生すれば想定外のインパクトを引き起こす金融取引においてのネガティブな要因。
デマーク(DEMARK)
トム・デマークが考案したデマーク指標のこと。
トゥークプロフィッツ(took profits)
take(取る)profits(利益)の過去形。利益を確定させたという意味。
ドット・フランク法
リーマンショック後の2010年7月に制定された、アメリカ合衆国の包括的な金融規制法。
トップアウト(top out)
価格が天井をつけること。最高値に達すること。
ドテン
ドテン(途転)。売りポジションを決済し、新たに買いポジションをとること。 あるいはその逆。
トリガー(trigger)
オプションの権利が発生・消滅すること。
トレール注文(トレーリングストップ)
すでにポジションを持っている時、決済時の逆指値注文を、レートの上昇幅、または下落幅に合わせて、自動的に追従(トレール)させていく注文方法。自分が設定した水準以上の損失を回避しつつ、利益の最大化を図ることができる。
【ナ行】
仲値
日本国内で営業する邦銀・大手外資系銀行が、午前9時55分の為替レートを元に発表する対顧客電信相場(TTM=Telegraphic Transfer Middle Rate)。
ゴトー日(5日、10日といった5の倍数の日)、GW前後、年末年始の前後等では外貨買い需要の極端な高まりから、仲値にかけて相場が上昇(円売りが加速)するケースが多くみられる。
最近では余りないが、1990年3月の最終営業日に、途上国債務の償却から米ドル/円が仲値直前の5分で3円上昇した歴史もあり、古参の市場参加者ほど仲値の存在を重視する傾向がある。
ノストロアカウント
ノストロ・アカウントとは、現地通貨建てで決済する際の、当方勘定。
【ハ行】
バイ セットアップ(buy set up)
買いセットアップ 。TDシーケンシャルにおいて使用される言葉。日足の場合、4日(本)前より低い終値が連続すること。
バイ・ザ・ルーモア/セル・ザ・ファクト(Buy the Rumor / Sell the Fact )
「噂で買って事実で売る」という相場の格言。為替市場は、様々な市場の「期待」や「思惑」で動きます。 これが事実が出る前に、先に織り込む動きで、事実が出る前の「噂で買う」わけです。
そして事実が発表された時点では、その結果がどうであろうと、これまでの「期待」や「思惑」で先に織り込んで取られたポジションが利食いされます。これが「事実で売る」ということです。 このため、良い結果でも売られたり、悪い結果でも買われたりということが起こります。
バイオンディップ(buy on dip)
押し目買いのこと。「sell on rally」の反意語。
バニラオプション(vanilla option)
シンプルなオプション。
例:ドルコール円プットオプション → 米ドル/円でドルを買う権利
バリア(Barrier)
オプション取引の用語。 一般にオプションバリアー(option barrier)と呼ばれている。オプションバリアーは、オプショントリガーと同じ意味。 条件付のオプションにおいて、その値が付いたらオプションの発生や消滅が起こる条件となる価格のこと。
パリティ(parity)
日本語では等価の意味。EURUSD=1.00を例にすると、ユーロとドルの通貨間の価値が等しくなる場合を等価、パリティと言う。
PMI
購買担当者景気指数、製造業やサービス業の購買担当者を対象にアンケート調査を実施、受注高、価格、購買数量の変化等に一定のウエイトを掛けて算出する指数のこと。景況感の節目が50、これより上昇が景気拡大、一方下落が景気後退。
ビーオージェイ(BOJ)
Bank of Japanの略。日本銀行(中央銀行)のこと。
ビオ(bio)
billion(ビリオン)の略。1,000,000,000(10億)のこと。
bilと呼ばれるときもある。 usd 1 bio=USD 1,000,000,000
ヒストリカル・レート・ロールオーバー(HRR)
Historical Rate Rollover、銀行等金融機関の顧客が取引金融機関とディールした為替取引をそのまま用い、保有ポジションの決済日を延長すること。ただし、どの金融機関も再延長や再々延長は「損失の先送り」にも使われることから(金融庁の規制もあり)応じていない。
ビッド(bid)
買いの注文。89円台のbidが増えてきているというのは、89円台での買い注文が増えてきているという意味。
ファットフィンガー(Fat Finger)
入力、発注ミスのこと。指が太くて横のキーまで一緒にタイプしてしまうのが本来の意味。
ファンディング通貨
高金利通貨を買い建て、より低い金利の通貨を売り建てるいわばキャリートレードをする際のこの「より低い金利の通貨」を指す。いわば資金調達通貨で、リスクオフ時には巻き戻し=買い戻しから、独歩高になる。現状では円やスイスフラン。
フィボナッチエクスパンション(Fibonacci Expansion)
調整が入り、再び元のトレンドへ戻った時にどこまで価格が動くかを測る指標。 XOP 161.8%レベル OP 100.0%レベル COP 61.8%レベル
フェイル(fail)
fail(フェイル)は、読んだそのままの意味で「失敗」です。テクニカルの想定通りに相場が動かない場合、failしたとも言います。ディナポリの場合は、ダブルレポやシングルペネトレーションなどの方向性に関するサインが示されながら、その方向に相場が動かない場合をfailといい、従来の方向にさらに強く動く可能性がある、とされます。
フォワードガイダンス
中央銀行が将来の金融政策の方向性を説明する指針。
プット
オプション取引で、売る権利のこと、反対に買う権利はコール。
相場が下がりそうなら、プット・オプションを買っておけば、下がったところで権利行使して利益とすることができる。下がらなければ、権利行使せず、プットを買ったプレミアムだけで済む。
踏み上げ
価格の上昇により、ショートポジション(売りポジション)の損切り注文(買戻し)により、更に価格が上昇することを言います。スクイーズ squeezeともいう。
プライスアクション(price action)
値動きのこと。
プライスフリップ(price flip)
TDシーケンシャルで用いられる用語。
例:日足の場合 当日の終値<当日から4日前の終値 かつ 前日の終値>前日から4日前の終値 または、 当日の終値>
当日から4日前の終値 かつ前日の終値<前日から4日前の終値 この状態をprice flipといい、プライスが交差する状態のこと。
ブラックアウト期間
中央銀行の政策決定者による「政策金利発表前」の、メディア向けを始めとする自身の見解を公式に封印する期間。
フラット為替
フラット為替とはUSDJPYを例にとると、直物(スポット)が安いときに将来のかなり先(5-10年、それ以上の長期)までフォワードレートを加味し輸入予約を済ませてしまおうというスキーム。
ブリッシュ(bullish)
先行きに対する強気な見方。
フロー(flow)
大口投資家の注文。
プロプライアタリートレード
Proprietary Trade、略してProp Tradeともいう。Proprietaryは英語の形容詞で元来の意味は「独占的な、専有の」であることから、これにTradeと加えることで、本来の業務から独立したトレーディングを意味する。
投資銀行等では元来から普通に使われてきた言葉で、いわば投資銀行内で本来の顧客中心のトレードから独立した、「実需等の裏付けの無い完全な投機ポジションの継続が許された一部の専任トレーダー」の投資行動を指す。これは投資銀行内の「ヘッジファンド」で給与は単年契約の完全出来高払いが多い。
こうしたトレードをする組織が「プロップデスク」「プロップチーム」、トレーダーを「プロップトレーダー」と呼ぶ。世界の政治経済情勢に精通していることは大前提で、為替のみならず、株、債券、金利、商品等の広範な金融知識、デリバティブズといった金融派生商品の知識も幅広く求められる。
ベアリッシュ(bearish)
先行きに対する弱気な見方。
ペッグ(peg)
連動するということ。自由な為替市場で為替レートが決まるのではなく、 一定のレートに固定または連動することをpegと言う。
例) HKDがUSDではなく人民元にpegするということは、 HKDがドルとの連動ではなく、人民元に連動する、という意味。
ヘッジ外債
国内の機関投資家の外債投資の中で、ヘッジを付けている外債投資のこと。ヘッジが付いているので実質外貨買い・円売り要因にならない。反対が「オープン外債」
ヘッドラインリスク(headline risk)
ニュースなどの見出し(ヘッドライン)で相場が急変するリスク。
ヘリコプターマネー
マネタリズムを提唱した米経済学者、ミルトン・フリードマン氏の主張、「通貨供給量の膨張で物価は上昇」。制御不能となる物価上昇の観点が論議されず、近年でも持ち上げられるがやや非近代的理論。
ペンション(pension)
年金のこと
ホーキッシュ(hawkish)
タカ、タカ派的のこと。 強硬派、強気、積極的
例: 景気経済の見通しについて楽観的、強気 政策金利の引き上げに対して積極的 政策金利の引き下げに対して消極的
対義語:ダビッシュ/dovish/ハト派
ポジション(position)
持ち高のこと。USD/JPYの買い(売り)ポジション
↓ USD/JPYの買い(売り)の持ち高を持っている 。
ボトムアウト(bottom out)
底を打つ(底値になる)
ボラティリティ(volatility)
価格変動の度合い。
ボンドオークション(bond auction)
国債の入札。
本邦
日本の企業や投資家のこと。
【マ行】
巻き戻し(アンワインド)
通常、株価が上昇すると、買い持ちのポジションには評価益が発生する。投資家の損益が改善していることになり、リスク許容度が増加したことになり、事実上、さらなるリスク資産への投資が可能となるから。
一方で、株価が下落した場合は、これとは逆の動きとなる。評価益が減少(または評価損が発生)することで、リスク許容度は低下。リスク資産を手放さなければならず、発生する資金フローは既存のポジションを巻き戻す動きとなる。このことを「巻き戻し」または「アンワインド」と呼ぶ。
マクロファンド
主にファンダメンタル分析により、今後予想される資金移動を後半に予測し予め莫大な資金を投じるヘッジファンドのこと。動かす資金が桁外れに大きく、中長期のテーマを作りやすい。
マジノ線
一般的には、フランスがドイツとの国境に築いた難攻不落と呼ばれた要塞のこと。為替市場では、売り方と買い方が攻防する価格水準のこと。
マッシブ(massive)
規模や量が大きいこと。
ミドル(middle)
中央、中盤のこと。101円ミドル 、↓ 101.50付近のこと。
モデルファンド
特に為替市場において、テクニカル分析を主体としたヘッジファンドのこと。これは、コンピュータモデルやテクニカル分析を駆使し、市場で売買を繰り返すことにより収益獲得を狙う。マクロファンドと異なり投下資本はそれ程大きくない。
モメンタム株
勢いのある株。投機的な値動きをする株のこと。
【ヤ行】
ヤード(yard)
1,000,000,000(10億)のこと。billion と同じ意味。
インターバンク取引の1本は100万通貨なので、1billion(10億通貨)は1yard。eur 1 yards = EUR 1,000,000,000
優位性
「他の市場参加者に比べて、トレード環境その他のマーケットアクセスにおいて」優位な展開であるということ。
【ラ行】
リアルマネー(real money)
株式市場や為替市場において、年金基金や投資信託などの運用主体の資金。
リスクプレミアム
リスクのある資産の期待収益率から無リスク資産の収益率を引いた差を示す。
リクイディティ(liquidity)
流動性のこと。
リクイデーション(liquidation)
清算・利確・決済の意味。
リスクリバーサル
オプション市場において同一期間(よく使われるのは1か月)、同一条件下での、「コールのボラティリティからプットのボラティリティ」を引いた値。
例えばプットの超過幅が6.7%とはきわめて異常値で、コスト削減の為に割安になっているコールをその何倍も売ってファイナンス(資金調達、実質この場合、プットを買うための原資にしているということ。
こうした取引では、下落へのヘッジは万全だが、相場が想定外に反転した場合、下向きに準備した建玉を遥かに上回るコールを買い戻す必要が生じる。2017年のフランス大統領選直後の急激なユーロ高はこの取引が一部主因とされる。
リスクアセット(risk assets)
元本(投資資金)が保証されていない金融資産のこと。
リスクオフ(risk off)
世界経済への先行きの懸念から、投資家がリスクをとりたがらない状況。
リスクオン(risk on)
金融市場のセンチメントの改善から、投資家が積極的にリスク資産への投資を行うこと。
リスクファクター(risk factor)
金融市場のこの先の動向をみる場合の不確実性、その要素、要因
リバース・ノック・アウト(RKO)
Reverse Knock-Out Option でオプションの1種。オプションの原資産の価格が、オプションの契約期間中に一度でもオプション価値に有利な方向で、所定の価格に達すると権利が消滅するオプション。プレミアムが安くなっている場合が多い。
ドル円で例えると、原資産(ドル円)の価格が104円の時に、月末までに107円を越えなければ、102円で買える権利のようなもの。期限(この場合は月末)までに一度でも107円をつけてしまうと、ノックアウトされ、プレミアムを払ったにもかかわらず、102円で買える権利は消滅する。
レジスタンス(resistance)
抵抗線のこと。
レンジフォワード
USDJPYでは円高リスクをヘッジするためにドルプットオプション(ドルを売る権利)を買う一方で、そのプレミアム(オプション料)を軽減するために、ドルコールオプション(ドルを買う権利)を売却するというもの。コストゼロで円高方向のリスクヘッジが出来る。
ロールオーバー
オプションや先物の満期が近づいてきたタイミングで (満期後にポジションを持ち越すために) 期近のものを閉じて、期先のものに入れ替えること。
ロング( long )
買い
ロングサイドオンリー(long side only)
買い方のみ。
ロンドン仲値、ロンドンフィクシング
別名、WMR(World Market-Reuters)Fixing、世界の機関投資家が、為替レートの変動を加味した各国の株価の時価総額のリバランスを実施する際の為替の値決め。概ね、月末の最終営業日とその前日に集中する。