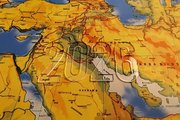ガザ紛争は今後の国際社会の紛争解決・復興のモデルになるか

7月22日、国際報道ではあまり取り上げられなかったが、国連安保理事会が、加盟193カ国に対し、国連憲章第6章に規定されている紛争の平和的解決を促す決議案を全会一致で採択した(決議2788号)。
同理事会では、グテーレス事務総長が、ウクライナ、スーダン、ハイチ、ミャンマー、ガザ地区での紛争に言及し、「今こそ、それが必要だ」と述べた。
この決議2788号では、全ての国に対し、紛争を平和的に解決するため、交渉、調査、仲裁、司法的解決、地域的取り決めへの付託、国連憲章などの方法を用いるよう述べられている。
世界には、グテーレス事務総長が言及しなかったインド・パキスタン間、タイ・カンボジア間などの紛争がある。
その中、改めて、国連安保理が国連憲章、国連決議、国際法を活用した紛争解決を示したことは歴史的にも意義がある。
現在、国際社会では、ガザ紛争の解決に向けての動きが活発化している。その動きは、紛争後の平和構築のあり方をめぐり、大きく2つに分かれている。
1つは「惨事便乗型資本主義」による復興といえるイスラエルと米国のであり、もう1つはフランスとサウジアラビアをはじめとするアラブ・イスラム諸国が目指すパレスチナ問題の「二国家解決」の動きである。
以下では、これら2つの動向について検討し、ガザ紛争の行方について考察することで、国際社会の紛争解決から復興について考える一助としたい。
危うい惨事便乗型資本主義の復興
惨事便乗型資本主義による復興とは、ナオミ・クラインが『ショック・ドクトリン』(2007)で指摘した、自然災害、戦争などの危機において、混乱を利用し、政治主体が規制緩和や民営化など企業の利益を優先し、市民の権利や抵抗力の衰退を招くような政策がとられることを指す。
中東地域では、2001年のアフガニスタン戦争、2003年のイラク戦争後の復興の失敗の要因として指摘されている。
具体的にアフガニスタンの例を見ると、当時、米国はタリバン勢力を一掃し、親欧米エリート層を中心とする政治体制を樹立し、国際的な専門家とドナー国の監視下で復興事業を行った。
その際、国際援助の3分の2はドナーが選んだ業者に送金され、支援がアフガニスタンの住民の手に十分渡らず、アフガニスタンの一部の人や欧米企業が不当な利益を得るという状況が生まれた。その結果、タリバンが復活し、4年近く支配を続けている。
一方、イラク戦争後の復興では、「連合暫定当局」が設立され、米国が巨額の復興資金を握り、イラクの法律を改正し、イラク経済を外国企業に開放させている。
そのことが、産油国であるにもかかわらず、経済は長期にわたり低迷し、「イスラム国」(IS)への多数の参加者を生むことになった。
この2つの惨事便乗型資本主義による復興には3つの共通点がある。
第1は、住民が主体的に将来を選択する可能性の低下である。
第2は、資金や土地などの復興資源を外国勢力や一部の支配層が収奪していることである。
第3は、安全保障の名目で、政権に対する反対勢力を弾圧していることである。
イスラエルと米国のガザ地区復興計画
ガザ地区の復興に関するイスラエルと米国の次のような最近の動きは、まさに上記の惨事便乗型資本主義の特徴を示している。
7月7日、イスラエルのカッツ国防相が、ラファ郊外の沿岸部に人道都市を建設するようイスラエル軍と国防省に指示している。
この計画は、最終的に、ハマス以外のガザ住民をこの狭い都市に収容するというものであり、それを厭うガザ住民に移住を促す意図がある。
7月23日には、極右政党「宗教シオニスト党」スモトリッチ財務相や入植地建設の活動家ダニエラ・ワイス氏らが参加し、ガザ地区でユダヤ人の恒久的な居住地を再建するためのマスター・プランが公開討論された。
さらに、7月28日には、ネタニヤフ首相が治安閣議を開催し、ガザ地区の「併合計画」を示している。
イスラエルのメディアによると、ハマスが一定期間内に停戦案に同意しなければ、現在、ガザ地区に設置されている「緩衝地帯」の面積を徐々に広げていき、併合にあたっては、住民の管理と治安維持のための専門機関を設置することが提案されている。
以上はイスラエルの動きであるが、ネタニヤフ首相は、この計画をトランプ政権も承認していると述べたと報じられている。
4つのガザ復興計画
イスラエルと米国が推し進めようとしているガザ復興計画は、次の4つがあるとみられる。
- ネタニヤフ政権が策定した「ガザ2035計画」
- ジョージ・ワシントン大学のペルツマン教授がトランプ政権に提示した
「ガザ再建のための経済計画」(「中東のリビエラ」) - 米国の親イスラエルのシンクタンクであるユダヤ国家安全保障研究所(JINSA)と
ヴァンデンバーグ連合が公表した「ガザ未来タスクフォース」 - 米国のシンクタンクのランド研究所による
「永続的なイスラエル・パレスチナ和平への道筋」
この4つの復興計画について、カーネギー財団のフェローであるヌール・アラフェ氏とマンディ・ターナー氏は、以下の点に注目している。
第1に、程度の差こそあれ、パレスチナ住民の同意なしの統治が構想されている。
第2に、外部から統制を強化する安全保障体制が設計されている。
第3に、外部からの土地や公的資金の収奪、およびその蓄積を促進できる経済システムが提案されている。
例えば、ネタニヤフ政権の「ガザ2035計画」では、イスラエルの行政組織が統治や治安を監督下に置くようになっている。
また、トランプ政権が公表した「中東のリビエラ」では、パレスチナの土地を投資商品として、外国投資家への完全売却を可能にしており、投資家がガザ地区の統治、インフラ、経済を管理することを提案している。
他の2案も同様で、パレスチナの機関の役割は明示されていない。さらに、これら4つの計画とも、イスラエルがハマス等の抵抗勢力を無力化するための継続的な軍事力行使を支持している。
そして、こうした復興計画の問題となるのがパレスチナ住民の存在であり、「ガザ2035計画」「中東のリビエラ」では、パレスチナ住民の域外移住に言及している。
この域外移住に関し注目されたのが、「ガザ2035計画」の策定に関与したと報じられている「ボストン・コンサルティング・グループ」(BCG)が試算した財務モデルである(ネタニヤフ首相はBCG出身)。
同モデルでは、住民に1人当たり9000ドル支払えば、50万人以上がガザ地区から移住するとされている。また、パレスチナのシンクタンクが実施したガザ地区住民を対象とする世論調査では、43%が地域外に移住したいと回答したとも報じられている。
ネタニヤフ政権のガザ併合計画では、ガザ地区沖の天然ガスの収奪、アブラハム合意の枠組み拡大によるアラブ諸国との地域経済連携とも結びつく。
ネタニヤフ首相にとって、ガザ復興計画による利益は、ガザ地区でのパレスチナ人の死者が6万34人(負傷者は14万5870人)に達した惨事に対する国際的な非難をものともしないほど大きいといえる。
・・・
全文を読みたい方は「イーグルフライ」をご覧ください。
メルマガ&掲示板「イーグルフライ」より一部抜粋しています。
(この記事は2025年7月31日に書かれたものです)