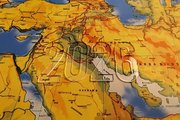ガザ紛争の停戦と米国の今後の中東政策 ―バイデン政権からトランプ政権に渡された課題の行方―

1月15日、米国、エジプト、カタールが仲介してきたガザ紛争の停戦合意が成立した。停戦は、1月19日午前8時30分を予定していたが、3時間近く遅れた11時15分の実施となった。
合意から実施の間にもイスラエル軍によるガザ地区への攻撃は続き、120人以上のパレスチナ人が死亡した。
停戦実施の翌日は、米国のトランプ氏の2期目の大統領就任式にあたり、停戦交渉へのトランプ氏の影響力に注目するメディアも少なくない。
しかし、停戦合意は、米国のバイデン大統領(当時)が2024年5月末に提示し、6月に国連安全保障理事会で採択された決議2735号(賛成14、棄権1)をベースに、仲介国が粘り強く交渉を進めてきた成果といえる。
ただし、3段階から構成されている停戦が、恒久和平に結び付かない懸念も指摘されている。2023年11月の戦闘休止が短期間で終わり戦闘が再開された経緯も踏まえれば、イスラエルとハマス間の信頼醸成は容易ではない。
また、第1段階(6週間)でイスラエル側の受刑者および被拘束者737人とハマス側の被拘束者33人が交換されることに比べ、第2段階ではイスラエル側がガザ地区から全面撤退し、ハマス側は全ての拘束者を解放することになっており、かなりハードルが高い内容となっている。
果たして、今回合意された停戦内容は、あくまでもバイデン政権の理想主義的構想であり、2段階目の実現さえおぼつかないものなのだろうか。
また、こうした困難な停戦をトランプ新政権は引き継ぐだろうか。
以下では、バイデン前政権の中東政策を振り返り、ガザ紛争により変化した中東情勢を踏まえ、トランプ政権がどのような中東政策をとるかについて検討する。
「統合された中東地域」を目指したバイデン政権の中東政策
ここでは、2025年1月14日(東部標準時)にブリンケン国務長官(当時)が大西洋評議会(アトランティック・カウンシル)で行った講演を参照しつつ、バイデン政権の中東政策を振り返る。
ブリンケン長官は、2023年10月7日以来12回も中東地域を訪問して実現しようとしたのは「統合された中東地域」だったと述べている。
同長官は、過去の中東政策において、中東諸国の政府や社会の変革を試みたが失敗してきたことを踏まえ、米国と地域のパートナー国との関係、パートナー国同士の関係を統合化へと変化させることを目指したと語る。
中東地域が統合されることで、この地域の人々に経済的機会がもたらされ、パンデミックやインフラ整備、エネルギー分野などの共通の課題に対する解決策を見出すことにもつながると考えていたという。
また、統合化が進めば、(1)核拡散の抑止、(2)侵略の阻止、(3)紛争の回避・緩和・終結を導く強い立場も生まれると構想されていた。
その構想実現のための具体的施策としては、アブラハム合意の深化、I2U2連合(インド、イスラエル、アラブ首長国連邦、米国の連合)、イエメン内戦の停戦の仲介、イランとの核合意再開交渉、サウジアラビアとの戦略的パートナーシップの強化などが取り組まれていた。
とりわけ、長期的に中東地域の安定化をもたらす統合のひとつの柱としてのサウジ・イスラエル関係の正常化を念頭に、サウジとは
(1)戦略同盟協定、
(2)防衛協定、
(3)民生用原子力開発を含むエネルギー協定、
(4)2国間貿易・投資強化の経済協力
などについて協議を重ねていた。
イスラエル・パレスチナ問題の解決が不可欠
ブリンケン国務長官は、地域統合化にはイスラエルとパレスチナの両者が現実を直視し、厳しい決断を下さない限り、「ゴルディアスの結び目」(難題)を解くことはできないと考えていたと述べている。
そのため、イスラエルには「パレスチナ国家との共存」を、パレスチナには「自治政府(PA)改革」を求め続けてきた。
同長官は、とりわけ多くのイスラエル人の心の中に、過去の和平努力がパレスチナ側に拒絶され、暴力的抵抗に結び付いてきたとの確信が存在していることがイスラエル・パレスチナ問題を難しくしていると見ている。
例えば、キャンプ・デービット合意では、パレスチナのインティファーダ(民族蜂起)、レバノンとガザ地区からのイスラエル軍の一方的撤退がヒズボラやハマスの誕生に結び付いたと指摘している。
このため、2023年10月からはじまったガザ紛争の終結には、イスラエルの人びとの確信を変える必要があり、そのためには、地域内外のパートナーが前例のない形で団結し、安全保障体制をつくる必要があったと述べている。
同長官は、実際、バイデン政権は、中東地域の内外のパートナーとガザ紛争の停戦計画を協働で、次のような原則にもとづいて進めてきたと語っている。
(1)ハマスが再びガザ地区で台頭することを防ぐ
(2)パレスチナ自治政府(PA)は、ガザ地区の主要民間部門
(銀行、水道、エネルギー、医療)の担当者と暫定政権を設立し、
運営と支援を行う
(3)また、暫定政権の行政担当者は、
復興の取り組みを監督する国連高官と緊密に協力する
(4)治安については、パートナー国と審査を受けたパレスチナ人を
構成員として治安部隊を編成する
(5)その任務は、人道支援、復興活動のための安全環境の整備と
密輸を阻止する国境警備とする
(6)治安部隊の訓練および装備、人員審査は、PAが主導する
(7)こうした内容を、国連安保理決議として採択する
1月15日の停戦合意を支えるものとして、以上のような計画が、イスラエル、パレスチナ双方に提示されている。ただし、ブリンケン長官は、この計画には次のような課題があると指摘している。
(1)ガザ地区とヨルダン川西岸地区の再統一を含むPAの改革
(2)独立したパレスチナ国家形成の道筋をイスラエルが受け入れること
(3)国際社会が政策協調してハマスの復活を阻止すること
これらは、今回、停戦合意の協議で協働したトランプ政権に引き継がれる課題ということになる。
仮に、停戦合意の第2段階へと進めば、第3段階はこうした紛争後のガザ地区の統治を含めてパレスチナ国家の樹立が協議されることになる。
・・・
全文を読みたい方は「イーグルフライ」をご覧ください。
メルマガ&掲示板「イーグルフライ」より一部抜粋しています。
(この記事は2025年1月21日に書かれたものです)
関連記事
https://real-int.jp/articles/2730/
https://real-int.jp/articles/2747/