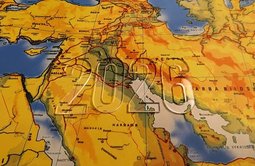中央銀行の一大事は波及するのか

★★★上級者向け記事
豪中銀の行動は是か非か
2日、RBA(豪州準備銀行)は2024年4月償還国債の利回り目標(0.1%)を撤廃すると決めた。
ロウ総裁は「経済状況の改善とインフレ目標に向けて予想よりも早い進展があったことを反映するものだ」と説明したが、ようするにRBAが市場を制御することが、もはや不可能になったというわけであり、これは世界の金融市場・中銀にとって、事態が押し寄せてきたことを意味する。
RBAは新型コロナウィルス禍に見舞われた2020年3月に、利回り局線操作(イールドカーブコントロール=YCC)を導入した。
具体的には、3年物国債をベンチマークとするYCCと、より長めのゾーンを対象とした資産買入策をもって金融市場を管理していこうというものだ。
2024年4月償還の利回りを政策金利と同じ0.1%に誘導することで、2024年序盤までは、政策金利を引き上げないという時間軸政策の役割を担ってきた。
ところが、10月に入り同銘柄の利回りは目標の0.10%を超えて上昇。
RBAは10月22日に、利回り抑制のため同銘柄の買入オペに踏み切ったものの、27日の消費者物価指数(9月CPIトリム平均=前年同月比2.1%上昇と6年ぶりの、2%超えとなった)後、28日には0.5%を超えた。
にもかかわらずRBAによる抑制のための買入オペはその後も一切なく、それどころか、2024年11月償還債も1.2%水準を超え、より長い年限の利回りも揃って上昇していった。
OIS(翌日物金利先物)に至っては2022年つまり来年の複数回の利上げを織り込む水準まで上昇していった。
直近10月のRBA理事会声明では、
- インフレ率が目標である「前年比+2%~+3%」のレンジで安定的に推移するまでは政策金利を引き上げない
- そのタイミングは速くても2024年までは訪れない
とした。
RBAとしては、とりわけ利上げのタイミングに関する示唆の部分で、
足もとの利上げ早期化期待をコントロールするつもりだったのであろう。
RBAはこれまで、インフレはコロナ禍による一時的な要因によるものであり、基調ベース(CPIトリム平均の前年比)では目標レンジには到達しないとの見立てを貫いてきた。
さらに、本格的なインフレ加速には一段の労働市場タイト化と前年比+3%程度の賃金上昇が必要とし、そうした条件が整うのは2024年以降とのシナリオも描いていた。
10月22日のRBA総裁発言でも、このスタンスに変化はなかった。
統計局によると7-9月のインフレ加速を牽引したのは、燃料価格と(木材等原材料要因による)、新築住宅価格の上昇だった。
その意味では、引き続きコロナ禍における一時的な要因とは言える。
また、消費者物価指数発表後の10月28日に議会に出席した総裁は、「もう少しのインフレは歓迎する」と発言した。
したがってRBAとしては雇用環境とりわけ賃金の動向を精査するという基本スタンスを変えてはいないはずだった。
それが突如、11月2日にYCC政策を撤廃したということは、雇用環境がどうあれ、事実上、利上げ早期化期待という市場のスタンスを追認したことになる。
これは先進国の中央銀行として一大事であることは間違いない。
・・・・・
続きは「イーグルフライ」の掲示板でお読みいただけます。