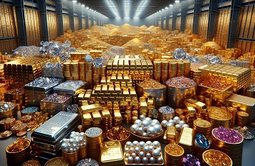政治的駆け引きだけのCOP26

★★★上級者向け記事
出来もしない目標
10月31日、英国でCOP26(第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議)が、異例の首脳級会合(11月1~2日)を含めて開催される。
首脳級会合は2020年の「パリ協定」がスタートして初めての開催であり、協定の実効性を占う会議となる。岸田首相も総選挙の結果が判明する中で出席の予定。
その一方でCOP26開催を前に主要各国のエネルギー政策を意識した動きと、コロナ禍後の経済回復の動きが重なり、「エネルギー危機」が一気に台頭。インフレだの、スタグフレーションだのと頭の痛いリスクが懸念されている。
10月26日、UNEP(国連環境計画)が「排出ギャップ報告書」を公表した。9月時点で温暖化ガスの実質排出ゼロをと宣言していた50カ国・地域を分析した内容だ。これらの国・地域は世界の排出量の半分以上を占める。
約束が実行されると、今世紀末に2.7度と予測する気温の上昇は、わずか0.5度分しか抑えられないとの試算だと報告。
その上で「実質排出ゼロの目標は漠然としており、各国は具体的な計画を2030年以降に先送りしているのが実態。各国は新たな政策を導入し、数ヵ月以内に実行に移さねばならない」と総括した。
つまり、COP会議は能書き自体もいい加減で、実効性が伴っていないというわけである。実際、その通りなのである。
ババ抜きのカードゲームなり!
今年4月、菅首相(当時)は2023年の温室効果ガス削減の目標として、2013年度比46%削減を表明した。
これは、2013年度比26%削減とした6年前の目標を大幅に引き上げるものであるが、果たして、コロナ禍で傷む日本経済は、この野心的な目標に対応できるのか。
1997年の京都議定書で2000年の日本の目標値を90年比でマイナス6%としたが、これは極めて厳しい目標で、できるのはせいぜいマイナス0.5%ぐらい。
しかし、EUがマイナス15%を打ち出してきて、米国は当時のゴア副大統領が、「京都会議を成功させるために議長国たる日本はもっと野心的な数字を出さなければダメだ」と言ってきて、結局日本マイナス6%、米国マイナス7%、そしてEUは姑息にもマイナス15%を引っ込めて、マイナス8%となった。
ところが、米国はブッシュ政権が中国や発展途上国の協力なしでは意味がないとして、京都議定書から離脱。
一方、EUは東西ドイツの統合とか、英国の石炭から天然ガスへの転換でマイナス8%を、ほぼ達成する見通しとなった。京都議定書の目標達成ができなくて困ったのは日本だけとなった。
そして最終的には、日本だけが海外からCO2クレジットを買わざるを得なくなり、1兆円を超える国富が海外に流れてしまった。完全に日本の外交的敗北だった。
インテリジェンスが足りなかったことは、太平洋戦争敗北のプロセスと見事に重なる。
2008年~2011年の温暖化交渉、これは京都議定書の第一約束期間(2008年~2012年)が終わる2013年以降を、どうするかの交渉だった。
ここでは麻生首相の下で半年以上かけて議論し、2005年比マイナス15%の目標で固めていた。
ところが政権交代で民主党政権となり、その議論がひっくり返されて、マイナス25%削減の目標を国際公約してしまった。
鳩山首相は、日本が野心的な目標を出せば(2000年交渉時のEU=マイナス15%案をマネたか)各国も、目標レベルを引き上げると読んだが、引き上げた国は1つもなく、日本の独り相撲で終わってしまった。
マイナス25%を実現するため、政府のエネルギー基本計画では原子力発電のシェアを、2020年までに50%まで引き上げる計画に修正せざるを得なくなってしまった。
その代わり、日本は目標実現に前提条件(すべての国が参加する・衡平で実効性のある枠組みとする)を付けると提案。
ようするに米・中という巨大なCO2排出国も参加し、応分の削減し、途上国も協力せよという条件主張だったが、途上国が「道連れにするナ」と激しく抗議し、降ろさざるを得なかった。
温暖化交渉全体を通じて言えることは、決して「地球環境を守るために各国が力を合わせましょう」という美しいものではなく、各国は完全に国益で動いているということだ。
温室効果ガスの削減は、地球レベルでの「外部不経済の内部化」であり、そのコストを各国の間でどう負担するかというゲームである。
自国が削減しても他国が削減しても地球レベルでは全く同じゆえ、当然フリーライダー(タダ乗り)が生じる。自国が削減するインセンティブはなく、他人に汗をかかせたほうがいいのである。
・・・・・
続きは「イーグルフライ」の掲示板でお読みいただけます。